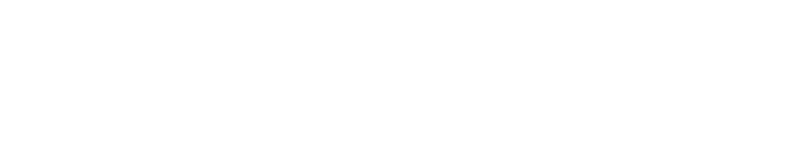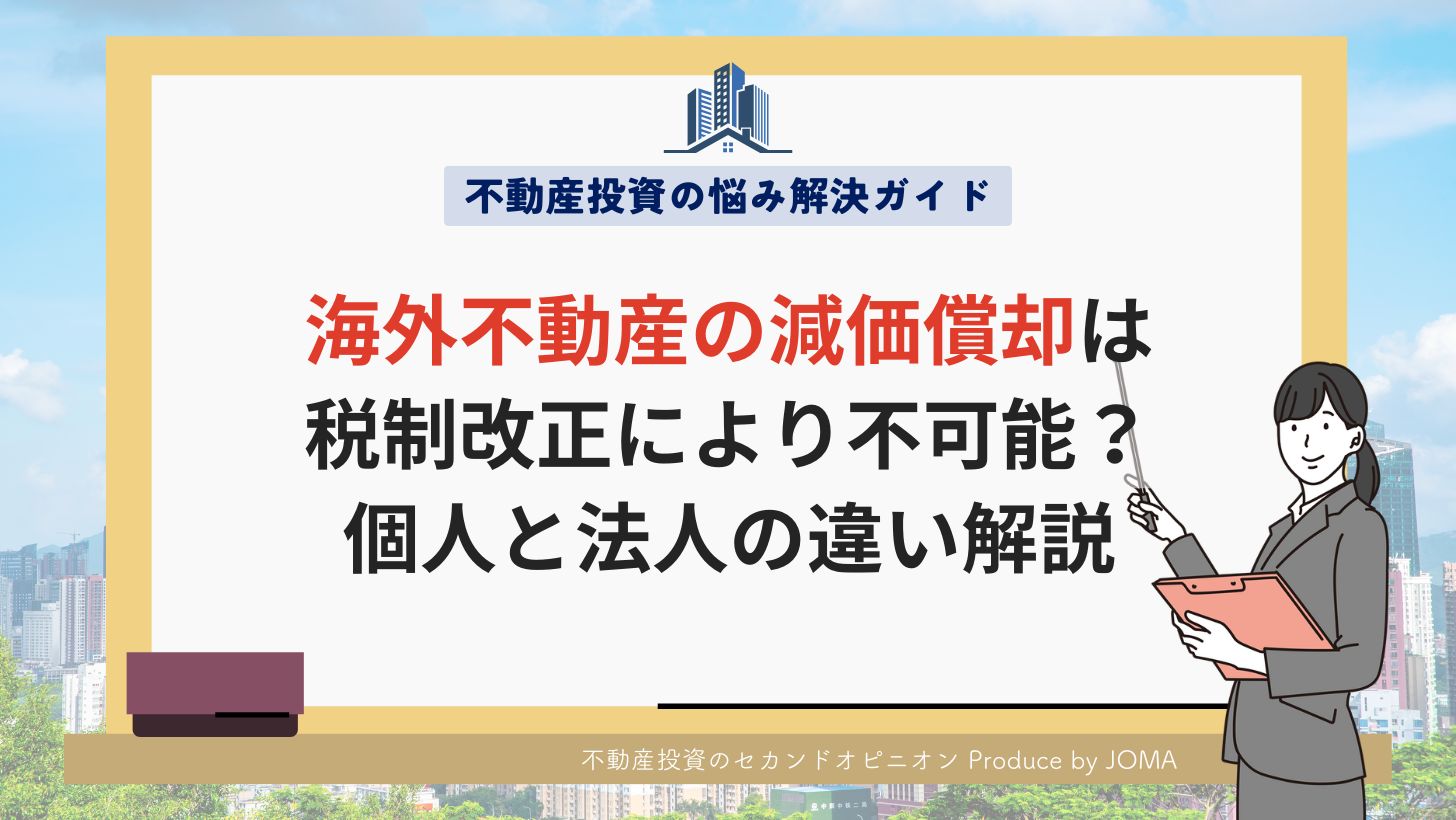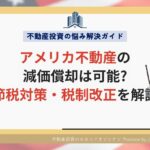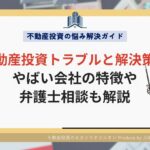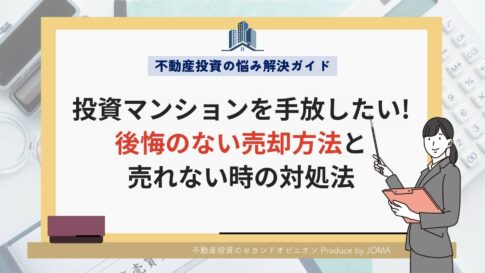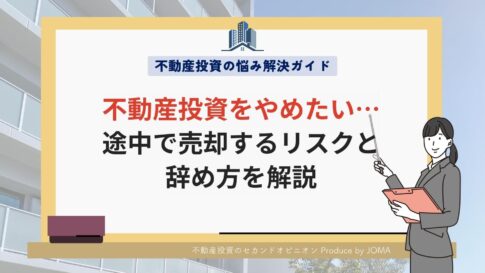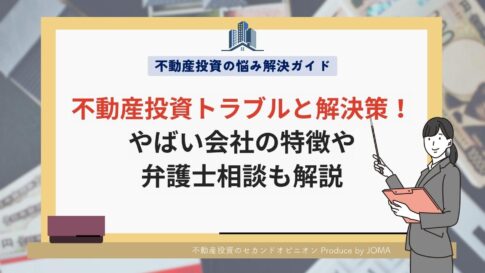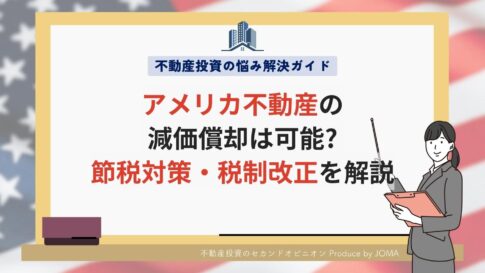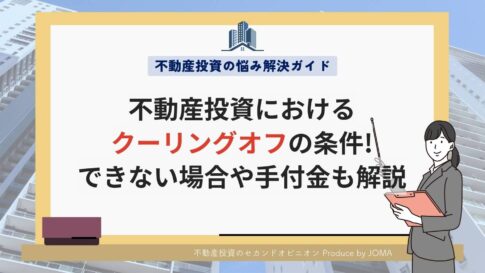この記事では、海外不動産の減価償却が税制改正により不可能となったのか、個人と法人の違いを中心に解説します。さらに、耐用年数を簡便法で償却可能であった点など海外不動産が節税対策として注目されていた理由や、国税庁による税制改正の内容などについても紹介します。
海外不動産は、簡便法による減価償却の損益通算が節税対策として富裕層に人気でしたが、税収の減少を課題視した国税庁は税制改正を行い、個人による節税を制限しました。一方で、法人では引き続き節税できるとともに、個人でも海外不動産で利益を得る方法はあります。
海外不動産への投資を検討している方へ、税制改正後の個人と法人の規制の違いや海外不動産を所有する個人の対応策などについて解説し、記事の終盤では海外不動産投資を行う際の注意点についても紹介します。
【不動産投資のご相談】はJOMAへ!
日本ワンルームマンション研究所(JOMA)は、ワンルームマンション開発に関わるデータ収集、分析、コンサルティングを行っている研究所です。 当研究所ではさまざまな角度から収集した情報をもとに、不動産デベロッパーの支援を行ってまいりました。
その活動の中で、不動産投資家向けの情報発信もして欲しいという要望を多く頂いたため、 今までの活動の中で得たノウハウをもとに、不動産投資をこれから始めようとされる方向けの情報発信の場として、当メディアは発足しました。

・どんな物件を選べば良いのかわからない
・不動産投資を始めるべき?
・提案されている物件が真っ当な物件か判断して欲しい
・マッチングアプリで出会った人の紹介って大丈夫?
こういった質問を多く頂きます。
不動産投資全般についてアドバイスできますのでお気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから
公式LINEでは、不動産の最新情報、ネットには出てこない未公開物件情報なども不定期で発信しています!
目次
海外不動産の減価償却とは

海外不動産における減価償却は、対象となる固定資産や減価償却期間、計算方法などが宅地建物取引業法で詳細に定められています。そのため、海外不動産への投資を行ううえで、減価償却を理解しておくことは非常に重要です。
ここからは、海外不動産における減価償却について、その定義と計算方法を解説します。
減価償却について
減価償却とは、長期で保有する固定資産の取得金額を、複数年にわたって費用計上する制度です。
固定資産は、毎年利益を生み出しながら価値が減少していくものなので、購入費用もその期間に合わせて均等に計上することが、減価償却の目的です。なお、減価償却できる資産には建物や建築付属設備などがあり、土地や建築中の建物などは減価償却の対象外となっています。
また、本来の用途や目的で固定資産が利用される期間と定められているのが耐用年数です。耐用年数は固定資産の種類によって異なり、それぞれ減価償却期間として利用されています。
減価償却の計算方法
減価償却の計算方法には、「定額法」と「定率法」の2つがあります。
定額法とは、法定耐用年数の期間にわたって毎年同じ金額を減価償却する計算方法です。それに対して定率法は、未償却残高に毎年一定の割合を乗じて減価償却費を計算します。定率法では、当初の期間は計上できる減価償却費が大きく、徐々に減少していきます。
なお、中古の固定資産については「簡便法」を利用することも可能です。簡便法では、経過年数が法定耐用年数を超過している場合、法定耐用年数の20%の期間で減価償却するので、短期的に経費を計上できます。
海外不動産の減価償却は税制改正により節税不可?
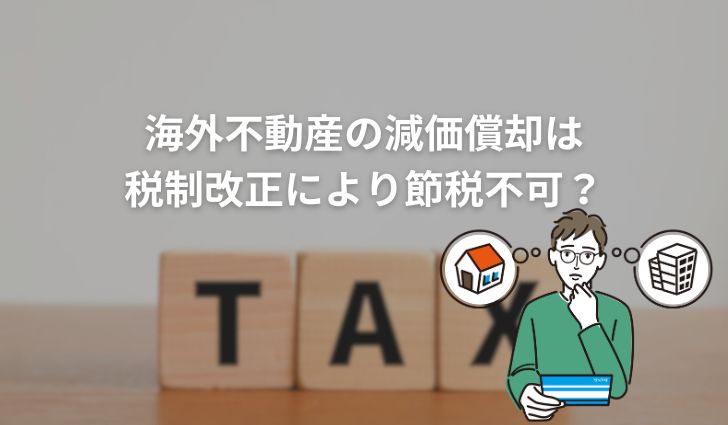
海外不動産への投資に興味がある方であれば、税制改正によって、海外不動産の減価償却は節税できるのかどうかを知りたいことでしょう。
ここからは、税制改正後の海外不動産の減価償却について解説します。
令和2年度税制改正による新たな規制
令和2年度に実施された税制改正では、海外不動産からの所得に関する新たな規制が、租税特別措置法に定められました。
具体的には、個人が海外中古建物による不動産所得で損失を発生させた場合、簡便法による減価償却部分は損失が発生しなかったものとみなす規制です。つまり、簡便法を利用して短期間で大きな減価償却費を計上しても、損失とはならなくなりました。
この改正により、海外中古不動産を購入して減価償却による損失を計上し、給与所得などと損益通算することで所得税や住民税を圧縮する節税スキームが利用できなくなりました。
海外不動産の減価償却ができなくなった背景
海外不動産の減価償却ができなくなった背景として、会計検査院からの指摘が挙げられます。
税制改正前は、給与所得や不動産所得を持つ高所得者が海外の中古不動産を購入し、減価償却費を計上することで所得税や住民税の負担軽減を図る節税スキームが横行していました。また、耐用年数が経過した5年後には売却し、別の不動産で同様の節税を行うことも可能です。
この状況を重く見た会計検査院は、平成27年度の検査報告において、海外の中古不動産に対して日本の減価償却の簡便法を適用するのは合理的ではないと指摘したことで、税制改正が行われました。
海外不動産投資が節税対策として注目されていた理由
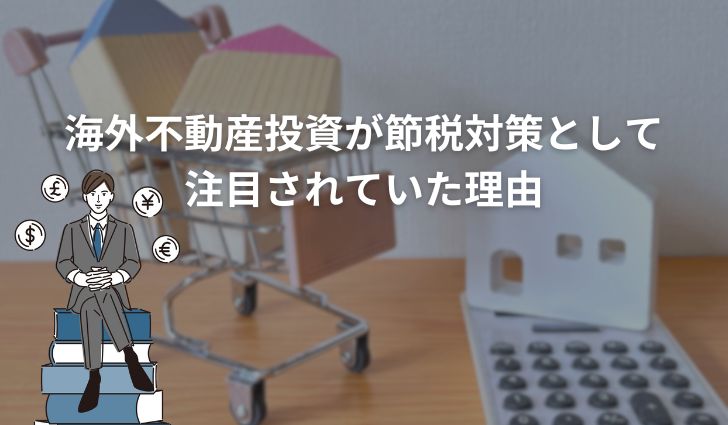
税制改正で海外不動産の減価償却ができなくなりましたが、改正前は高所得者を中心に海外不動産投資は節税対策として注目の的でした。
ここからは、海外不動産投資が節税対策として注目されていた理由について解説します。
海外不動産の資産価値が高い
そもそも海外不動産投資では、海外不動産の資産価値が高い点が注目されています。
経済成長が著しい国や人口増加が続いている地域では、不動産価格が安定的に上昇しているため資産価値の上昇が期待できます。また、海外不動産は土地に比べて建物価格の比率が高いことが多いので、減価償却の恩恵を受けやすく節税対策として有効でした。
なお、インフレ傾向のある国でも不動産価値は維持しやすいため、資産防衛の手段としても重宝されています。
耐用年数を簡便法で償却可能
海外不動産投資が注目されていたのは、耐用年数を簡便法で償却可能であった点も理由です。
簡便法とは、中古資産を取得した際の耐用年数を計算する方法の一つであり、法定耐用年数を全部経過した固定資産については、法定耐用年数×20%に相当する期間で減価償却が可能です。
築22年以上経過した木造建築物の場合、簡便法で計算される耐用年数は4年となるため、新築不動産と比べて短期間で減価償却費を計上することができました。
給与等の所得と損益通算ができた
海外不動産投資で発生した損失を給与などの所得と損益通算ができた点も、注目されていた理由の一つです。
損益通算とは、1年間で得られた利益からほかの所得で発生した損失を相殺することであり、利益に対して本来生じる税負担を軽減することができます。
海外不動産の購入費用を減価償却することで発生した損失を、給与所得などと損益通算することで所得が減少し、所得税や住民税を軽減できる節税対策とすることが可能でした。
売却時にも税負担を軽減できた
海外不動産投資で購入した物件は、売却時にも税負担を軽減できる点も注目された理由です。
海外で不動産を売却することで得られたキャピタルゲインは、譲渡所得として所得税の対象となります。譲渡所得に対する税率は不動産を所有していた期間によって異なり、特に5年超の長期譲渡所得は、給与所得と比べて低税率です。
そのため、不動産保有期間中は損益通算で節税し、5年経過後に売却することでさらに税負担を軽減できていました。
国税庁がメス!税制改正後の個人と法人の規制の違い
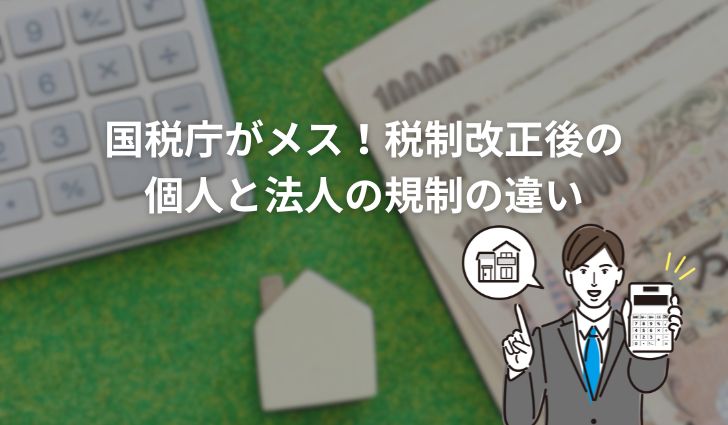
海外不動産投資が節税対策として利用されていた状況を重く見た国税庁は、令和2年度の税制改正により海外不動産の減価償却にメスを入れました。
ここでは、税制改正後の個人と法人の規制の違いについて解説します。
規制が個人にのみ適用される理由
税制改正による規制が個人のみに適用される理由は、富裕層からの税収が減少する恐れがあるためです。
税制改正前では、高額所得者である富裕層が国内における税負担を軽減するために、こぞって海外不動産を購入していました。これにより、日本の税収が減少するとともに、国内資産の海外流出も問題となっていました。
この状況を懸念した国税庁と会計検査院は、個人を対象とした税制改正を実施し、海外中古不動産の購入による節税スキームができないようにしました。
法人は従来通り簡便法を用いた減価償却が可能
税制改正により、個人は海外不動産の減価償却が制限された一方で、法人は従来どおり簡便法を用いた減価償却が可能となっています。
租税特別措置法では、海外不動産に関する規制について「個人は」と対象を限定しており、法人は対象外です。そのため、法人が所有する海外中古不動産は、簡便法による減価償却で発生した損失は認められています。
なお、法人は所得全体に税率を適用するので、事業所得と損益通算することで節税が可能です。
海外不動産を所有する個人の対応策

税制改正により、個人では海外不動産の減価償却で節税することはできなくなりましたが、それ以外にも海外不動産で収益を得る方法はあります。
ここからは、海外不動産を所有する個人投資家の対応策を紹介します。
保有し続けて家賃収入を得る
個人で海外不動産を保有し続け、家賃収入を得る対応策は有効です。
経済成長が著しい海外の国では、人口増加に比例して賃貸需要も高まっています。入居者のニーズに合った不動産を保有し続けることで、安定した家賃収入を得ることができるでしょう。
また、日本と比較して築年数が経過した不動産でも一定の賃貸需要が維持されるのも特徴です。そのため、海外不動産を長期保有しても、家賃収入が目減りする可能性は低いといえます。
法人名義で投資する
法人名義で海外不動産に投資する方法も、有効な対応策です。
令和2年度の税制改正により、個人での海外不動産投資は減価償却による損益通算が制限されました。一方で、法人による海外不動産投資は制限の対象外です。そのため、法人名義で投資することで、これまで同様の節税効果を得ることができます。
また、所得税より低い税率が適用されたり、経費計上や損失繰越などができたりするメリットも得られるので、法人化はおすすめです。
複数の不動産を保有して損益通算を活用する
複数の不動産を保有して、損益通算を活用するのも対応策の一つです。
税制改正により、海外不動産の減価償却による損失は、給与所得など別の所得とは損益通算できなくなりました。一方で、不動産所得との損益通算は引き続きできるので、海外不動産を複数保有することで、損益通算による節税をすることが可能です。
なお、日本に居住している方で、海外不動産投資で一定以上の所得が発生した場合は、日本での確定申告が必要となります。
売却してキャピタルゲインを得る
海外不動産を売却して、キャピタルゲインを得る方法もあります。
キャピタルゲインとは資産の価格変動によって得られる利益のことであり、不動産を購入した際の価格よりも売却時の価格が高い場合、その差額がキャピタルゲインとなります。
海外では、経済成長や人口増加を背景に不動産価格が上昇するケースも多く、適切なタイミングで売却することで大きな利益が得られる可能性があります。また、築年数が長い不動産でも価格が下落しづらい点も魅力です。
減価償却できないだけじゃない?海外不動産投資を行う際の注意点

海外不動産への投資を行う際には、個人では減価償却ができないことだけではなく、様々なリスクや課題があることを理解しておかなければなりません。
ここでは、海外不動産投資を行う際の注意点を4つ解説します。
為替リスクがある
1つ目の注意点は、為替リスクがある点です。
海外不動産投資は、現地通貨で取引されるので、為替の影響を受けます。例えば、不動産購入時よりも円安が進行すれば、売却時には円換算で利益が増えますが、逆に円高になると資産価値が減少する点がリスクです。
また、家賃収入や管理コストも為替の影響を受けるので、想定していた利益が変動するかもしれません。そのため、適切なヘッジ活用や複数通貨への分散投資などのリスク管理が重要です。
融資を受けることが難しい
2つ目の注意点は、融資を受けることが難しい点です。
海外不動産を購入する際に、国内の金融機関では融資対象外となるケースが多く、自己資金での購入を求められます。また、現地の金融機関から融資を受ける方法もありますが、外国人への貸し出しが制限されている金融機関も少なくありません。
そのため、海外不動産投資を行う際には、自己資金割合や返済計画などの資金計画を入念に考慮したうえで申込することが重要です。
管理会社の信頼性に欠ける
3つ目の注意点は、管理会社の信頼性に欠ける点です。
海外不動産投資では、賃貸管理や建物管理などを現地の管理会社に委託するのが一般的ですが、すべての管理会社が信頼できるとは限りません。各種管理業務が杜撰であったり、不透明な手数料などを請求されたりする場合があり、投資家にとって国内に比べて管理リスクは大きいです。
また、日本とは異なる法律や商慣習が存在することも踏まえ、事前に管理会社の実情や評判を調査する必要があります。
税制改正を意識しておくことが大切
4つ目の注意点として、税制改正を意識しておくことが大切です。
海外不動産投資に関する税制改正は、投資収益に大きな影響を与えかねません。実際に、令和2年度の税制改正では海外不動産の損益通算に関するルールが変更され、それまで活用されていた節税手法が制限されました。
また、現地国の税制変更により、想定外の新たな税負担が発生する可能性もあります。そのため、定期的に税務の専門家のアドバイスを受けることが重要です。
記事のまとめ
海外不動産の減価償却について、国税庁による税制改正の内容や個人と法人の規制の違い、海外不動産を所有する個人の対応策や注意点などについて解説しました。
海外不動産の減価償却は、節税対策として富裕層に人気でしたが、税収減を問題視した国税庁の税制改正により、個人による節税は制限されました。
一方で、法人は規制対象外であり、不動産需要の高い国では家賃収入やキャピタルゲインも見込めるので、海外不動産投資は魅力的です。海外不動産ならではのリスクに十分注意することで、法人はもちろん個人でも十分に収益を得ることかできるでしょう。
【不動産投資のご相談】はJOMAへ!
日本ワンルームマンション研究所(JOMA)は、ワンルームマンション開発に関わるデータ収集、分析、コンサルティングを行っている研究所です。 当研究所ではさまざまな角度から収集した情報をもとに、不動産デベロッパーの支援を行ってまいりました。
その活動の中で、不動産投資家向けの情報発信もして欲しいという要望を多く頂いたため、 今までの活動の中で得たノウハウをもとに、不動産投資をこれから始めようとされる方向けの情報発信の場として、当メディアは発足しました。

・どんな物件を選べば良いのかわからない
・不動産投資を始めるべき?
・提案されている物件が真っ当な物件か判断して欲しい
・マッチングアプリで出会った人の紹介って大丈夫?
こういった質問を多く頂きます。
不動産投資全般についてアドバイスできますのでお気軽にご相談ください。
ご相談はこちらから
公式LINEでは、不動産の最新情報、ネットには出てこない未公開物件情報なども不定期で発信しています!